シリーズ「平成をふりかえる」① 伸び悩む消費が歩んだ30年
2018年10月02日
住友商事グローバルリサーチ 経済部
鈴木 将之
概要
終わりを告げようとしている平成について、「消費」という視点から振り返ってみる。はじまりはバブル絶頂期で力強さを見せていた平成の消費は、次から次へと新しい商品が登場していたにもかかわらず、次第に「伸び悩む」という枕詞がついて回るようになった。度重なる経済危機や自然災害などもあって、先行きが見通しづらく、将来的に所得が増えていくという右肩上がりの期待が失われてしまったようだった。また、バブル崩壊から失われた20年へ移り変わる中で、土地など実物資産が価値を下げて家計の重荷になった一方、失業率の上昇など先行き不透明感に対するリスクも背負わざるを得なくなった。所得が伸び悩む中で、介護などが家庭内から社会化されたことの対価として社会保険料などの負担も増えてきた。そうした環境によって、平成の消費は、悪くいえば伸び悩む消費、良くいえば堅実な消費へと変わってきた。
しかし、平成も終盤に差し掛かると、状況に変化がみえはじめた。景気が回復し、人手不足も目立ちはじめたことで、賃金が上昇に転じた。ようやくデフレ(デフレーション)ではない状況になるなど、環境はこれまでになく好転している。将来に期待を持っても良いのだと、消費は前向きなものになりつつある。このように、バブル絶頂から困難な状況に突き落とされ、そこから再び立ち上がっていくプロセスが平成の消費から見えてくる。
1. 消費から平成をふりかえる
2019年に終わりを告げようとしている平成(1989年1月8日~2019年4月30日)。その期間は31年にわたり、昭和、明治、応永に続く4番目の長さになる見込みだ。
平成のはじめに、日本はバブル経済という絶頂期の真っただ中にいた。しかし、その崩壊によって負った傷は深く、その後長引く経済の低迷は「失われた20年」と呼ばれるようになった。また、経済成長が鈍化したこともあり、物価上昇率がゼロ%近傍にとどまり、賃金も伸び悩むデフレ状態に陥ってしまった。
昭和のキャッチアップ型の成長から、平成のフロントランナー型の成長へと、日本企業や経済が置かれた局面が変わった一方、少子化や高齢化、核家族化など社会も変化し、その対応に迫られていた。また、経済・社会の変化に加えて、地震などの自然災害も多く、乗り越えるべき困難は少なくなかった。これらの課題は、一朝一夕に解決できるものではなく、それなりの時間を必要としていた。
1997年には金融危機とアジア通貨危機、2008年にはリーマンショック後の世界同時不況と、10年ごとに経済的な危機が発生した。前向きになろうとしていたタイミングで、新しい困難に直面してしまった。夢と希望を抱くことが難しくなり、右肩上がりの成長は遠い昔のことのようだった。土地などの資産価値の低下にデフレが重なり、重い荷を背負って長い道を歩んでいるような状況が長かった。そのため、平成は停滞する日本と重なり、その印象が広がった。
一方、世界に目を転じると、同じように大きな変化があった。例えば、1989年ベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終結した。欧米を中心に資本主義・自由主義が繁栄を謳歌してきた一方で、先進国とは異なるルールでキャッチアップを進める新興国が出てきて、その存在感を高めてきた。象徴的なのは、先進国中心のG7からG20へと、世界経済の問題を話し合う枠組みが拡大していることである。米国の貿易摩擦の対象が、かつての日本から現在では中国やメキシコ、カナダなどに移っていることもあげられるだろう。
そうした中で、リーマンショック後の世界同時不況、欧州債務危機など、世界経済は混乱に直面し、これまでの価値観のほころびが目立ちはじめた。これまで成長を支えてきた自由主義や民主主義に代表されるような政治・経済などの既存体制への批判が、格差の問題、移民・難民の問題なども絡まり、高まっている。政治は左右の勢力が勢いづいたり、大衆迎合的な主張への支持が集まったりしている。それが、新たな不確実性を生み出し、世界経済の行方を見通しづらくしている。
しかし、平成を通じて、家計も企業も移りゆく環境にゆっくりと対応しはじめてきた。その成果が次第にあらわれはじめ、日本の名目GDPは3度目の挑戦でようやく過去最高記録を更新、デフレではない状況になるなど、経済全体にも変化の兆しがみえている。また、幸いにして、2017年には、大きな経済的な困難は発生しなかった。平成も終わりに近づくにつれて、ようやくバブル崩壊と失われた20年の傷も癒えはじめている。つまり、日本は次の成長の芽を見つけ出そうとしており、失われた20年で忘れかけていた夢と希望を再び追い求められる環境になりつつある。こうしたことを踏まえて、以下では、次の成長の芽に注目しながら、個人消費を通じて、平成をふりかえってみる。
2. 次々と登場してきた新商品
平成になってから、「伸び悩む」は「消費」の枕詞として使われてきた。そこで、まず、「ヒット商品番付」(SMBCコンサルティング:図表1)から、その時代に流行ったものや当時の世相をみておこう。
平成が始まったころ、日本がバブル期にあった1990年には、アンテナ付きの携帯電話が普及しはじめた。それまでは弁当箱のような大きなものだったが、手で持ち運べるような小さな新製品が普及しはじめた。これはその後、携帯電話自体の価格の低下、通信料金の低下によって、爆発的に広まる前触れといえる。また、新型の家庭用ゲーム機が発売されて大きなブームとなり、備え付け型のゲーム機が日常生活の一部になっていった。また、葛西臨海水族園のようなエンターテイメントセンターも開業しており、多くの人が足を運んだ。このように、この頃の個人消費には、バブル景気の余韻が残っており、まだ前向きで力強いものだったといえる。
団塊ジュニアが進学・就職期に差し掛かった1993年には、バブルが崩壊して、景気が悪かったこともあり、節約志向が高まった。酒や家電などのディスカウントストア(激安ショップ)が増えたことからも、そのような消費者マインドの変化がうかがえる。一方で、ポケットベルも流行するなど、屋外で使う通信機器が生活に浸透していった。これらによって、他人とのつながりが強くなる半面、プライベートな空間が屋内から屋外に広がることで、次第にライフスタイルや消費行動が変化していった。
金融危機の渦中で、金融機関や大企業でさえ倒産するほど日本経済がどん底にあった1998年には、半額マックバーガーに象徴されるようなデフレマインドが色濃くなった。前年の消費税率引き上げもあったことで、消費税還元セールも好調だった。また、アジアでは通貨危機が発生して、これまで成長が著しかった東南アジア諸国もつまずいた。そうした中では、完全失業率が高まり、企業はリストラを進めるなど、右肩上がりの成長が過去のものになった。そのため、これまでとは異なる世の中が到来したという感覚が広がっていったようだ。そうした雇用・所得環境が悪化する中で、値引きをしなければ売れない状況に、消費は陥った。ただし、個人消費が低迷して、全く物が売れなくなったのかというと必ずしもそうではなかった。例えば、ポリフェノールなど、健康や高機能製品への消費者の意識も高まり、これまで以上に選別された消費が顔をのぞかせるようになった。ただし、ヒット商品の横綱不在という当時の状況が、個人消費の弱さを物語っている。

ITバブル崩壊から回復しつつあった2003年には、小型デジタルカメラや薄型テレビなど、家電が好調さをみせていた。こうした動きが追い風になったこともあり、家電メーカーの生産拠点の国内回帰がみられるなど、経済の回復も進みつつあった。個人消費に目を向けると、ヘルシア緑茶など、健康面からも注目された商品が登場する一方で、コンビニエンスストアの高級おにぎりが発売されるなど、良いものは少し高くても買うという消費者マインドの変化の兆しが出ていた。その背景には、小泉政権下で後から見れば戦後最長となる「いざなみ景気」が始まる中、デフレマインドが払拭される可能性が高まっていたことがある。ただし、「実感なき景気回復」という言葉が象徴するように、景気は回復すれども、賃金上昇ペースは緩慢で、実感できるほどのものではなかった。そのため、当時、「失われた10年」という言葉で、日本経済の低調さが語られていた。金利がゼロ%まで下げられるなど金融政策がこれまでになく大胆なものになったものの、デフレマインドは根強く残り、それが消費の重石になっていた。
リーマンショック後の世界同時不況が発生して、再び日本経済が窮地に陥った2008年には、1998年以来のヒット商品の横綱不在になり、個人消費の絶不調さが印象づけられる。アウトレットモールや5万円パソコンなど、デフレマインドが再び勢いを増したようだ。その一方で、共働き世帯の増加などから、外食から中食にシフトする動きや、家庭で簡単に調理できるものが売れるようになるなど、ライフスタイルとともに消費も変化しつつあった。ヒット商品にも、それほどお金を使わず、近場で楽しめるようなものが多くみられる。言い換えれば、堅実な消費であり、皮肉にもそれが経済成長の足かせになってしまった。
そうした個人消費に、再び転機が訪れる。第2次安倍政権が成立、経済政策としてアベノミクスがはじまった2013年は、これから何かが変わるような期待が高まった。60年に1度同じ年になる出雲大社・伊勢神宮の遷宮があったり、富士山が世界遺産に登録されたり、豪華観光列車が登場したりするなど、インバウンド消費の拡大もあって、人々の目が再び観光に向かい、国内旅行も見直された。その一方で、団塊の世代が65歳を迎えた中で、高級食パンへの需要が増加、コンビニカフェなど、新しい生活スタイルの確立にもつながった。消費も節約一辺倒ではなく、いわゆる「ハレの日消費」や「プレミアム消費」など、使うときには使うことも増えてきた。
2017年には、「今を大切にする消費」といううねりの中で、「インスタ映え」などコト消費の広がりがみられる。下ごしらえした食品が届く料理キットなど、共働き世帯のニーズをとらえた商品も広がった。景気が回復する一方で人手不足が顕著になり、高齢者や女性の就業が増えたため、家事を代替するような商品やサービスへの需要が高まった。また、自動運転技術やAIスピーカーなど新しい商品も登場しており、新しい生活スタイルへの道筋が見えはじめている。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催など、良い意味で将来に目が向く機会が増えた。景気回復が続いていることも、前向きな見方の支えになっていた。
平成を通じて、バブルからその後の失われた20年と、良いときも悪いときも経験したことで、人々の目は肥えて、堅実な消費になってきた。しかし、それは節約一辺倒ではなく、良いものにはお金を使う、支払うべきモノ・サービスにはしっかり支払うという、当たり前といえば当たり前の消費スタイルでもある。そのように考えると、国内市場は縮小して成長しないなどということは本質的なことではなく、消費者ニーズを捉える重要性を、平成という時代は再認識させてくれたようだ。
3. 豊かさの実感なき消費
今日、「実感なき成長」という言葉が端的にあらわしているように、豊かさの実感は得にくくなっているようだ。昭和の豊かさの象徴といえば、耐久消費財があげられるだろう。新しい家電を次々と購入して、生活が便利になっていく。それが、豊かさの一つの形だった。
例えば、1950年代後半の神武景気に生活必需品として宣伝された「三種の神器」(白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)や、1960年代後半のいざなぎ景気における「3C」(カラーテレビ、クーラー、自動車)など、それまでの生活を一変させた象徴的な製品があった。洗濯は冷たい水を使って手でするものではなく、機械任せとなり、テレビ放送によって、様々な娯楽を家庭で楽しめるようになるなど、大きな変化が家庭で実感できた。
このように、耐久消費財が拡大してきた。しかし、失われた10年、20年と呼ばれるようになった平成になると、なぜ消費が伸び悩んでいるという印象が強くなったのだろうか。その一因は、生活を一変させるような商品が、少なくなっているからかもしれない。
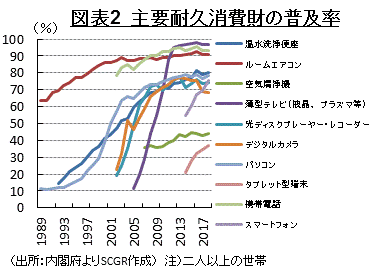
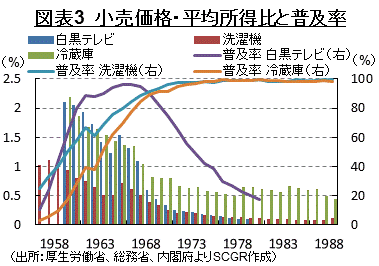
しかし、図表2のように、平成になっても新しい耐久消費財が市場に登場し、普及してきたことは事実だ。1989年に普及率が63.3%だったルームエアコンは、2012年には90%を越えた(以下、普及率については内閣府『消費動向調査』)。花粉やPM2.5などの問題を背景に広がった空気洗浄機も、2012年には40%を上回った。温水洗浄便座も2016年には81.2%と8割以上の家庭に備え付けられている計算だ。また、2005年に11.5%だった薄型テレビは、2011年7月の地上デジタル放送の完全移行という追い風もあり、2012年には95.2%とほぼすべての家庭に行き渡った。パソコンや携帯電話、スマートフォン(スマホ)などのIT機器も爆発的に普及している。その他にも、サイクロン型掃除機やロボット掃除機など、家事労働の負担軽減ニーズとあいまって、比較的高い価格帯の商品の売れ行きも好調だった。ただし、平成に普及した商品は、かつての三種の神器に比べるとインパクトは小さいようだ。
その一因は、まだ普及途上であるため、インパクトを実感する段階にはないのかもしれない。実際、テレビは比較的早く普及したものの、その他の商品の普及には時間がかかった。普及率が10%から80%まで上昇するまでに、白黒テレビは4年(1958年10.4%→1962年79.4%)、電気洗濯機は10年(1957年20.2%→1967年79.8%)、電気冷蔵庫は9年(1960年10.1%→1969年84.6%)だった。また、カラーテレビは5年(1969年13.9%→1974年85.9%)と早かった一方で、ルームエアコンに至っては26年(1972年9.3%→1998年81.9%)、乗用車は、28年(1965年9.2%→1993年80.0%)もの時間を要した。このように、普及には時間がかかることを踏まえると、平成に生まれた商品は、まだ普及の途上にあるとみられる。
しかし、昭和と平成の消費で異なることは、かつては耐久消費財が豊かさの象徴であったことだ。例えば、豊かさの実感は、その商品を購入することで生活が変わることはもちろん重要であるものの、それを手に入れた達成感も重要だと考えられる。
図表3、4のように、男性一般労働者の年収(きまって支給する現金給与月額×12か月+年間賞与その他特別給与額)から月給を算出し、各商品の小売価格(総務省『小売物価統計調査』)を買うために何か月分の給料が必要になるかを計算してみた。
それぞれ統計が遡れる時点を始点とし、普及率が約80%に達した時点を終点として比べると、白黒テレビは1961年の2.1か月分から1962年の2.1か月分とほぼ横ばい、電気冷蔵庫は1961年の2.2か月分から1969年の1.0か月分、電気洗濯機は1958年の1.0か月分から1967年の0.7か月分だった。一方で、ルームエアコンは1970年の2.1か月分から1998年の0.4か月分、カラーテレビは1969年の2.7か月分から1974年の1.3か月分であった。乗用車は1970年の9.6か月分から1993年の4.9か月分となった。このように、多くの商品は発売当初は高額であったものの、その後劇的に価格が低下することで普及していった。その過程の途上では、1か月分の給料を全てつぎ込んでも購入できない「高嶺の花」であった。
それに対して、平成になると消費単価は低下している。薄型テレビは発売当初、1か月分の給与では全く買えないものだった。しかし、新商品が出るたびに価格は劇的に低下し、画面サイズは大きくなっていった。携帯電話やパソコンも当初は、高額商品だったものの、爆発的な普及とともに本体価格が急激に値下がりしていった。スマートフォンも1か月分の給与で十分買える価格帯になっている。容易に入手できることも、それ自体豊かさの一つだろう。しかし、豊かさの実感はかえって得にくくなったのかもしれない。
また、生活の利便性は高まったものの、新たな変化というものが起きにくくなっている印象がある。例えば、爆発的に普及したスマホも、電話自体は従来からあったし、パソコンもスマホ登場以前にあった。新たな分野を切り開いて、生活を激変させた商品というよりも、これまでの生活をもう一歩便利にした商品という性格が強い。このように、かつて、三種の神器が家庭に入ってきたときのインパクトよりも小さく、生活を大きく変えるインパクトに欠ける商品が増えているようだ。
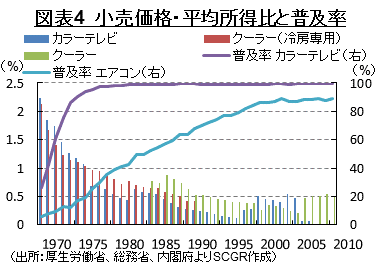
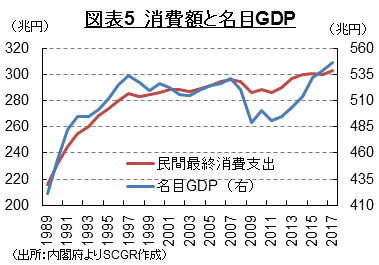
ただし、平成の消費額が緩やかに増えてきたことは事実だ。図表5をみると、伸び悩みというイメージは、消費の実体を必ずしも正確に捉えていないことがわかる。まず、消費額をみると、経済全体(GDP)に比べて堅調に推移してきたことがわかる。実感に近いとされる名目GDPが1997年に534.1兆円とピークをつけてから、2016年(538.5兆円)に更新するまで約10年かかった。それとは異なり、消費(名目民間最終消費支出)は2000年に286.6兆円と、1997年(285.2兆円)を上回ったからだ。
リーマンショック前の2007年(296.0兆円)の水準も、2013年には296.7兆円と上回っており、個人消費は総じて緩やかな成長トレンドをたどってきた。また、1989年と2017年を比べると、名目GDPが1.3倍になったのに対して、個人消費は1.4倍とGDP成長を若干上回る拡大傾向がみられる。つまり、緩やかながらも、消費は拡大してきたといえる。しばしば言及されるように需要が飽和したわけではなく、携帯電話・スマホからロボット型掃除機など、消費者の心を惹くような商品が登場すれば、多少高くても購買意欲はかき立てられてきた。その一方で、日用品などへの消費意欲はそこまで強くなかったこともあり、消費が全体としては力強さを欠いてきたように見えただけだったのだろう。
このように、豊かになっていることは事実であるものの、生活水準が格段に上がったという実感は得にくくなっているようだ。ただし、以下でみるように、平成が始まってから30年経ち、ようやく消費が変化する兆しも見えはじめていると考えられる。
4. 取り戻しつつある前向きさ
平成を通じて、さまざまな経験や環境の変化を踏まえて、消費スタイルは緩やかに変わってきた。
例えば、「すでに4人に1人以上が65歳」という高齢化に目を奪われがちであるものの、世帯構成の変化も重要だ。実際、世帯数の変化をみると、1989年に全体の20%を占めていた単独世帯は2016年には26.9%まで増え、その一方で三世代世帯は14.2%から5.9%に減っている(厚生労働省『国民生活基礎調査』)。単独世帯で特に目立つのが、高齢者世帯の増加である。65歳以上の人がいる世帯において、1989年には14.7%に過ぎなった単独世帯の割合は、2016年に27.2%とほぼ倍増している。
また、新しい技術の広がりも、消費スタイルの変化を後押している。その象徴的なものはスマートフォンやパソコンなどIT機器の利用頻度の高まりだろう。2016年には、学業・仕事以外の目的で使用した人の割合は60.1%と、もはや生活に欠かせないものになっている(総務省『社会生活基本調査』)。
それによって、通勤・通学時間に、情報収集や買い物ができるようになるなど、消費行動が変化している。かつて電車の中は読書の時間であったが、現在はインターネットの時間に変わっている。実際、1年間の通信費(2人以上の世帯)は、2000年の11.4万円から2017年の15.9万円へと39.3%増えている(総務省『家計調査』)。それに対して、書籍・その他の印刷物は5.5万円から4.2万円へと23.6%も減っている。一部の書籍や雑誌は、紙媒体からスマホなどで閲覧できるデジタルへと変わっているので、以前と同じように本を読んでいる人も多いのかもしれない。しかし、実感としては、インターネットの時間になっているようだ。
こうした社会の変化の中で、日本全体の消費額の構成も緩やかに変化してきた。5年おきにみると、2008年にかけて、食費の構成比が減ってきた一方で、住宅・水道光熱費は増えてきた。2013年以降になると、食費の割合が増えはじめている。これは景気回復の中で、共働き世帯の増加に伴う中食などの消費需要の増加や、単独世帯数が増加した影響とみられる。
また、高齢化の中では、保健・医療費の割合が緩やかに増えている。携帯電話・スマホ、インターネットの普及などもあって、通信費の割合は1989年から2015年にかけて3倍弱に増えており、家計支出での存在感を高めている。消費の足かせとして、携帯電話の通信料金が議題として取り上げられるのも、こうした背景があるからだろう。
このように、新しい技術と世帯など社会的な変化を色濃く映しながら、モノよりもコトというサービス化の流れの中で、消費が変化してきた様子がうかがえる。
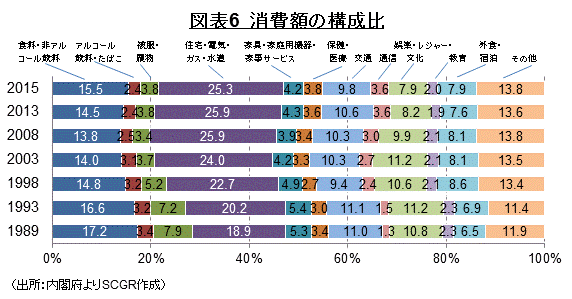
また、消費マインドも大きく変化している。よく物欲が無くなってしまったのかとか、需要が飽和したとか語られることが多い。実際、図表7のように、内閣府『国民生活に関する世論調査』によると、確かに「物」よりも「心」の豊かさを重視する傾向があるようだ。確かに全体(平均)をみると、心の豊かさやゆとりを求める傾向が続いているように見える。
しかし、年齢別では異なる印象を受ける。例えば、20歳代では心の豊かさを求めている一方で、物質的な面の豊かさも求める傾向が強まっている。30歳代や40歳代では、物質的な豊かさを求める傾向が2000年代半ばから増加に転じている。それに対して、50歳代以上では物質的な面よりも心の豊かさやゆとりを求める傾向がある。つまり、若年層は、物の消費を求めていないわけではなく、確かに消費需要は存在しているのだ。
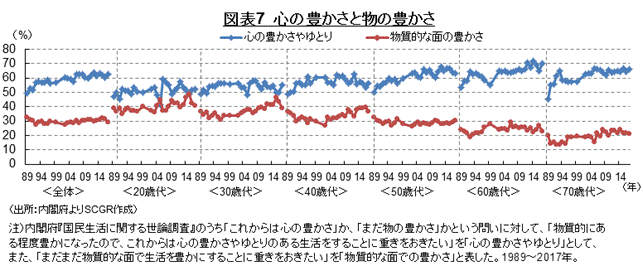
次に、将来への備え(未来志向)と毎日の生活の充実(現在志向)に注目してみる。図表8のように、全体では現在志向の高まりと未来志向の底打ちがみられる。未来志向は2000年前半にかけて低下していたものの、それ以降下げ止まっている様子がうかがえる。
年齢別にみると、若年世代の未来志向の高まりが、全体の底打ちの一因であった。ただし、若者の未来志向が、リーマンショック前の2006年頃から始まり、世界同時不況からの回復期まで進んでいたことが注目される。いわゆるアベノミクスの時期でも、上昇ペースは鈍化しているものの、トレンドを維持している。この時期には、いざなみ景気という戦後最長の景気拡張期間を記録し、リーマンショック後の世界同時不況、さらに東日本大震災、アベノミクス景気など、消費者マインドは大きな影響を受けてきた。この期間を通じて、途中足踏みがあったとはいえ、好況が長く続いたことで、将来見通しが改善されて、未来志向が高められた可能性がある。
その一方で、不況や震災などによって、リスク回避的な思考より、将来に備えることの重要性が認識され、未来志向が高まった可能性もある。また、足もとでは、再度、戦後最長をうかがうほど景気拡張局面が伸び、所得もこれまでになく増えていることから、前向きな未来志向が高められたと考えられる。
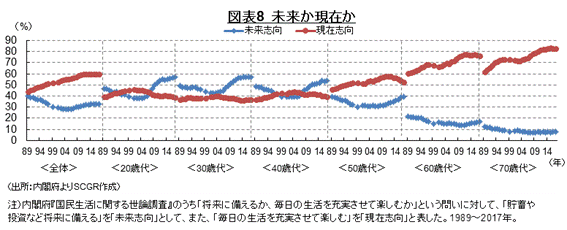
このように、消費スタイルが変化する中で、消費者は未来志向を少しずつ取り戻しつつあるようだ。物の豊かさを求める気持ちも若者には残っている。今を楽しむコト消費などサービス化の流れの中で、モノとコトをうまく合わせた消費を模索しているのかもしれない。そうした前向きな姿勢の消費が増えるような環境は整いつつあるのだろうか。以下では、消費を巡る環境について注目してみる。
5. 所得①: 変化する所得の中身
「実感なき成長」の背景には、所得の伸び悩みがある。図表9のように、1989年から1991年にかけて、可処分所得は毎年20兆円規模で拡大していた。
例えば、1990年には、雇用者報酬が前年から+16.9兆円、財産所得が+13.7兆円と所得増の牽引役だった。また、金利が高かったこともあり、利子支払などを含む財産所得支払は+5.7兆円増えた一方、預貯金の受取金利もそれなりにあった。その一方で、図表10のように、所得増に伴って、所得税等も+5.7兆円、社会保険料などの社会保障負担も+4.4兆円増えていた。ただ、負担以上に、収入が増えていたので、全体の可処分所得は増える傾向にあった。
しかし、平成も10年を過ぎようする頃に、変化が現れはじめた。可処分所得は、1999年に前年差▲2.3兆円と減少に転じ、2003年まで減少しつづけた。不況のあおりをうけて、失業率が上昇し、雇用者報酬が減少したことが主因だ。また、金融政策の舵が緩和方向に切られ、1999年にはゼロ金利政策が導入されたことで、預金金利が縮小し、財産所得受取も前年割れの状態が続いた。
このように、雇用者所得が伸び悩む一方で、堅調に増えてきたのが、年金・医療・介護などの社会保障給付だった。もちろん、この背景には、高齢化や世帯の変化などがあり、社会の要請に応じたものだった。実際、高齢化率(65歳以上人口割合)は、1989年の11.6%から2017年には27.7%まで上昇している(総務省『人口推計』)。つまり、日本では、4人に1人が高齢者という計算だ。
また、前述のように、世帯の形態も、大きく変化している。三世代世帯が1989年の438.5万世帯(65歳以上の人がいる世帯のうち40.7%)から2017年の262.1万世帯(11.0%)へと減少する一方で、夫婦のみの世帯が225.7万世帯(20.9%)から773.1万世帯(32.5%)、単独世帯が159.2万世帯(14.8%)から627.4万世帯(26.4%)へ増加している(厚生労働省『国民生活基礎調査』)。
三世代世帯では、介護など高齢者に対して家庭内で供給されていたサービスや生活費の充当などが、単独・夫婦世帯では外注されるようになった。その結果として、社会保障給付費が増えたという一面がある。
それを費用面からみれば、三世代世帯では高齢者に対する家庭内サービスに対して直接支払っていた費用を、社会保険料や税金として間接的に支払うようになったことを意味する。後者であれば、所得再分配などの効果が期待できるという良い面もある一方、前者のままであれば所得再分配が期待できず、純粋に金がモノを言う世界になってしまう。つまり、社会保障制度という第三者を介することで、所得再分配効果が働くことになる。
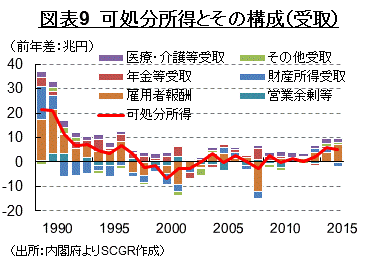
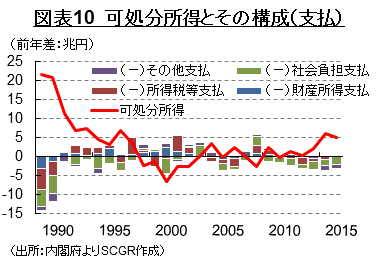
また、増税は記憶によく残っているのに対して、減税は忘れられがちだ。実際、平成になってから、消費税率は引き上げられたものの、所得税を中心に減税の連続だった。
例えば、1994年の総合経済対策による税制改革では▲2.4兆円、単年度の税額控除で約3.8兆円の減税が実施された。1999年には緊急経済対策として2.7兆円の定率減税を実施、2006年には三位一体改革の一環として3.1兆円の減税となった。内閣府『平成24年度経済財政白書』によると、1980年以降(大部分は1990年度以降)では、所得税の累積減税規模は約11.7兆円であった。
足もとで、バブル期並みに日本全体の所得が増えたのに、税収が増えていないのは、所得税減税が原因といえる。実際、図表11のように、1989年から2016年にかけての可処分所得の増減を要因分解すると、雇用者所得の増加(+61.4兆円)に対して、所得税支払(+1.6兆円)の増加は、少額にとどまった。
その一方で、年金等受取(+39.8兆円)や、現物として受け取っている医療・介護等受取(+38.3兆円)が増えてきた。もちろん、その対価である社会保険料などの社会保障負担の支払(+33.0兆円)も増えている。この間のすべての効果を勘案すると、可処分所得は+91.3兆円増加した計算だ。
特に、「実感なき成長」と言われた2000年代に注目してみると、戦後最長の景気拡張期間を記録した、いわゆる「いざなみ景気」の2002年から2007年にかけての可処分所得の内訳では、雇用者報酬(▲4.3兆円)、営業余剰(▲3.1兆円)が減少していた。この間、完全失業率は2002年の5.1%から2007年の3.7%まで低下したものの、いわゆる正規社員が▲40万人減少した一方で、非正規社員が284万人増加しており、平均賃金を押し下げる方向に影響していた。
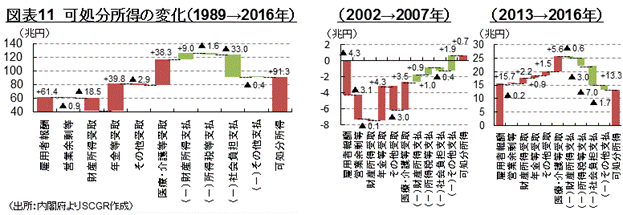
また、年金等受取(+4.3兆円)、医療・介護等受取(+3.5兆円)が増加した。つまり、実際の稼ぎが減った一方で、社会保障による給付が拡大していた構図だった。支払面では利払い費など財産所得支払や、所得税支払が減ったことで負担は縮小し、可処分所得は0.7兆円増にとどまった。医療などの実物給付を除けば、可処分所得は減少していたので、まさに「実感なき」状況だった。
それに対して、現在の景気拡張局面では、異なった動きがみられる。雇用者報酬(+15.7兆円)、財産所得受取(+2.2兆円)、医療・介護等受取(+5.6兆円)が増加要因となり、所得税や社会保障負担の支払が減少要因となったものの、可処分所得は13.3兆円増加している。
つまり、「実感」はそれなりにあるとみられる。完全失業率は2013年3.7%から2016年の2.8%まで低下した。同期間に、雇用者数は183万人増えており、その内訳をみると2002~07年には▲40万人と減少していた正社員が、人手不足の深刻化から2013~16年には+65万人と増えている。人手不足から雇用待遇の改善が進んでいることが、「実感ある成長」の一翼を担っていると考えられる。
6. 所得②:失いかけた夢と希望
平成が始まったころ、所得は増えるものだと思われていた。しかし、それが幻想にすぎなかったのではないかという思いが、平成を通じて醸成されてきたようだ。
これからの自分がどのように働き、稼ぐのか、そしてどのような生活が送れるようになるのか。そのとき、参考になるものは、職場などのちょっと年上の人々だろう。
例えば、1989年時点で、20~24歳の人が5年後の自分の年収がどの程度になると期待するのかといえば、身近なところで1989年の25~29歳の年収である。この1989年時点で20~24歳の年収と25~29歳の年収の乖離率を「5年後の期待年収上昇率」とここでは呼んでおこう。その一方、1989年に20~24歳だった人が、5年後には25~29歳になる。そこで、1989年の20~24歳の年収と1994年の25~29歳の年収の変化率を「現実の年収上昇率」とする。この2つの年収を比べることで、期待が現実のものとなったのか、それとも儚く散ってしまったのかということを捉えられるだろう。
図表12のように、10年ごとに男女別・年齢別に所得がどのように変化したのかについて、図示してみた。それによると、1989年は男女ともすべての年齢層で、現実の年収上昇率が期待年収上昇率を上回っており、「現実が期待を上回る」世界だったといえる。しかも、若年世代ほど、期待に比べて現実の年収の上昇率が大きかったため、将来への期待を膨らませることができた。つまり、「右肩上がりの世界」だったと考えられる。
それに対して、金融危機やアジア通貨危機などに見舞われた1998年では、もはやそうした関係はみられなくなった。さらに、2008年はリーマンショック後の世界同時不況の中にあったこともあり、期待は厳しい現実の前に崩れ去っている。自分の年収は、職場の5歳上の先輩ほどにはならない、そのような状況が1990年代後半から2000年代にかけて生じていたことになる。失われた20年で、何が失われたのかと問われれば、これから年収が上昇するという夢と希望が失われてしまったかのようだった。
しかし、幸いにして、状況は少しずつ変わりつつあるようだ。アベノミクスが始まった2013年以降に注目すると、現実の年収上昇率が期待年収上昇率を上回るような動きがみられるようになった。すべての年齢層にあてはまるわけではないものの、現実が期待を上回る年齢層、現実が少なくとも期待並みになっている年齢層が増えている。特に、これからを担う若年層ほど、そうした傾向が強いようだ。
平成も終わりに近づくにつれて、若者が将来の年収が増えるかもしれないという希望を持ってもそう悪くはないと思える方向に好転しつつあるようだ。そうした世代が増えることで、前向きな消費も拡大していくだろう。こうした傾向が続けば、たとえ緩やかな成長であっても、実感と希望を持って過ごせるようになるのかもしれない。
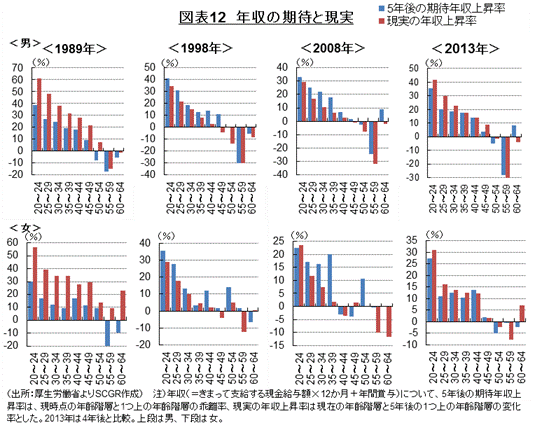
7. これまでも議論を呼んだ消費税
その他に、消費税も大きな負担として知られている。消費税は、商品やサービスを購入するたびに支払うので、一番身近であり、その負担感は認識されやすい。
図表12のように、消費税導入時には、実質的に負担減だった。所得税・法人税減税などを同時に行ったり、既存の間接税(物品税)を廃止したりして、消費税導入の負担感を和らげていた。3%の税負担(5.4兆円)よりも、減税規模が上回り、差し引きで2.6兆円の負担減となった。それまで、一般消費税や、売上税などの議論を通じた政治的な混乱などもあり、慎重な導入となった。
また、消費税の負担感を考える上では、物価動向がどのように変化したのかという視点も重要だ。消費税は商品やサービスの価格に上乗せされるため、物価上昇に影響を及ぼすからだ。消費税が導入された時点、1989年3月から4月にかけて、消費者物価指数(総合)は前年同月比1.1%から2.4%へと、また、実感に近いとされる消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は0.9%から2.4%へと上昇した。物価上昇率自体がそれほど大きくなかったこと、物品税の廃止と引き換えに消費税が導入されたこともあって、物価上昇への影響も限定的だった。
その一方で、1989年の名目賃金(事業所規模30人以上、就業形態計、調査産業計)は前年比4.2%、物価変動を調整した実質賃金でも1.9%で伸びていた。そのため、賃金上昇は消費税導入を含む物価上昇の痛みを吸収できていたといえる。
それに対して、1997年は実質的な負担増となった。3%から5%への税率引き上げによる負担増(5.2兆円)に加えて、それまで実施されていた所得減税の打ち切り、医療費の自己負担増などが重なり、ネットで8.5兆円の負担増となった。1997年3月から4月にかけて、消費者物価指数(総合)は0.5%から1.9%へ、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は0.2%から1.9%へと上昇した。
それでも1997年の名目賃金は2.0%と伸びており、実質賃金は0.4%と、なんとか物価上昇の痛みには打ち勝ったものの、所得減税打ち切りと医療費自己負担増という実質的な負担が重石になった。さらに、1997年といえば、金融危機、アジア通貨危機などによる不況が重なり、翌1998年の名目賃金は▲1.4%、実質賃金は▲1.9%と賃金の目減りを経験したこともあって、負担感は大きなものとなった。
2014年の5%から8%への引き上げは、3%分の負担増(8.2兆円)が大きく、軽減策があったものの、差し引きで8兆円の負担増となった。消費税率引き上げの単体による負担感が大きかった以上に、物価の押し上げ効果も大きかったことが、2014年の特徴だった。2014年3月から4月にかけて、消費者物価指数(総合)は1.6%から3.4%へ、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は2.0%から4.1%に上昇した。消費者物価上昇率2%を目指して金融緩和政策が実施されていた上、為替レートが円安に振れたことなどで、物価が上昇基調にあったためだ。
この結果、2014年の名目賃金が0.9%で上昇したものの、物価上昇の勢いに負けて、実質賃金は▲2.4%と、前年割れになった。デフレ脱却を目指して物価が上昇していた局面に、消費税率引き上げが重なったことで、実質的な購買力を損なうという不運に見舞われることになった。

2019年10月に予定されている8%から10%への税率引き上げは、日本銀行の試算によると、税率引き上げ負担増(5.6兆円)とともに、軽減税率(1.0兆円)、支援給付金(0.5兆円)、教育無償化(1.4兆円)などが実施されることで、差し引きで2.2兆円になるという。
これらを含む消費税率引き上げの影響は、過去2回の税率引き上げに比べて、それほど大きくない見込みだが、注目されるのは物価と賃金の動きだろう。日本経済はデフレではない状況になるなど、局面が変化している。物価が上昇局面にあり、そこに消費税率引き上げが加わることは、負担感が底上げされることになる。
また、景気回復の中で労働需要が増えている一方で、団塊の世代が労働市場から退き、高齢化と少子化が進み労働供給の天井がみえている中では、人手不足が深刻化し、賃金も上昇しやすくなっている。この賃金上昇が、物価上昇に打ち勝てば、消費税率引き上げの痛手はそれほど大きくならない可能性があるだろう。
このように、消費税の負担感の軽減については、その時の物価と賃金の動向が鍵を握る。しかし、負担感を議論するだけでは、本質的ではない。消費税は社会保障の経費であるため、その便益についても考えなければ、消費への影響は語れない。
8. 感じにくい私的負担と社会保障
社会保険料負担も、消費税などの税負担も増えて、生活が苦しくなった。そう感じる一方で、社会保障として、それらが還流しているという事実も忘れてはならない。つまり、少なからず、生活が支えられてきた一面もあるということだ。
社会保障制度が拡充されてきたことによって、親世代の生活・介護などの負担を直接するのではなく、税や社会保険料として、間接的に社会全体で負担するようになっている。これは、社会保険料などの負担が増える一方で、社会保障給付も増えていることを表している。
また、社会保障給付の増加によって、私的扶養・負担も減ってきていることも重要だ。例えば、自前でやらなければならなったことが、社会保障サービスで代替されるようになっている。このように、全体を俯瞰しておくことが重要だ。
そこで、まず、高齢者世帯の動向をみておこう。図表14のように、65歳以上の人がいる世帯数は年々増加しており、1989年の1,077万世帯から2017年の2,379世帯へと、2.2倍に増えている。内訳をみると、単独世帯と夫婦のみの世帯の「単独・夫婦のみ」は1989年には、子どもなどとの「同居」世帯と比べて少数派であったものの、2004年頃には逆転している。単独・夫婦のみの、いわゆる親世代のみの世帯が過半となっており、大勢を占めている。
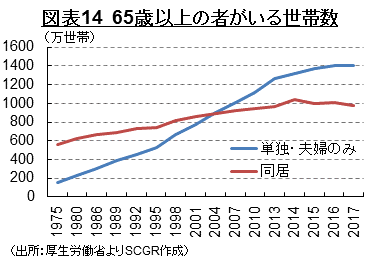
こうした高齢者世帯の所得は、どのようになっているのだろうか。高齢者世帯の所得には、自身で働いて得た所得、配当や利子などの財産所得、年金に加えて、仕送りもある。ただ、この仕送りは緩やかに減少している。具体的には、1989年の5.6万円から2016年の0.7万円まで減っている。1989年には景気が良かったことを踏まえても、大幅な減少といえる。
1世帯あたりの仕送り額と世帯数から、仕送り総額を計算してみると、1989年の2,000億円超から2016年には1,000億円程度へと、ほぼ半減していることになる。高齢者世帯数が増えているにもかかわらず、仕送り総額は減少しており、仕送り単価の低下の影響が大きいといえる。
次に、子どもが同居している場合の子ども世代の負担額について考えてみる。同居している場合、水道光熱費など、親世代の生活費の一部を子ども世代が負担しているケース、反対に親世代が子ども世代の生活費の一部を負担しているケースなどがあり、捉えることは非常に困難だ。そこで、ある程度幅をもって見る必要はあるものの、同居世帯においても、子ども世代が仕送り程度の負担をしていると仮定して計算してみた。つまり、ここでは、同居世帯数に仕送り額を乗じたものを、同居負担額の目安として使っている。
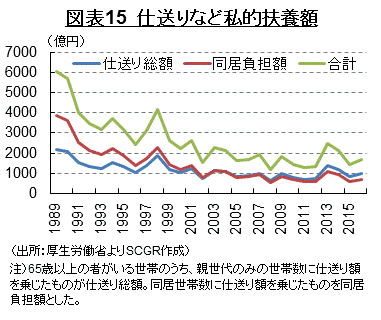
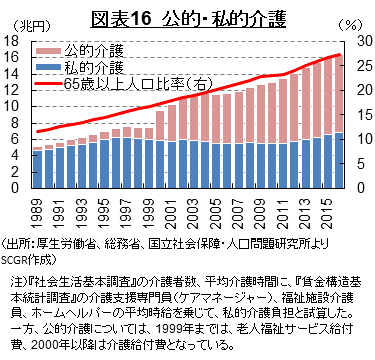
その結果、図表15のように、仕送り単価の減少によって、同居負担額も低下傾向にある。1989年に4,000億円近くあったものが、2016年には1,000億円を下回るようになっている。幅をもって見る必要があるものの、子ども世代の直接的な生活費負担は総じて減少している可能性がある。
なぜ、仕送り額は減ったのだろうか。仕送りする側、すなわち現役世代の所得が伸び悩んでいることが一因だ。自分の懐に余裕がない分、親の生活の面倒をみることが難しいのだろう。また、日本経済が高成長期であったこともあり、親世代の貯蓄額が増えていたこともあげられる。それとともに、年金給付額が増えている影響も大きい。これまで、年金制度が整備されてきたことによって、受給できる人も増えている。つまり、個人の仕送りが、公的な年金に代替された側面があると考えられる。
実際、年金給付額は、1989年度の20.1兆円から2015年度には54.0兆円と約2.7倍の規模に拡大している(国立社会保障・人口問題研究所『社会保障費用統計(平成27年度)』)。高齢化の進展とともに、私的扶養から間接的に社会全体で負担しあう「公助」に切り替わっている。そうした変化は、同期間に、高齢者世帯の1世帯あたりに占める年金所得の割合は54.5%から65.4%へと10%ポイント近く上昇していることからも、裏付けられるだろう。
また、平成になってから需要が拡大した社会保障制度に、介護がある。2000年以降、介護保険制度として整備されたこと、使い勝手のよさなどもあって、高齢化の追い風の中で介護給付費(図表16の公的介護)は拡大してきた。
介護給付という公的な社会保険に注目が集まる一方で、介護は家庭内でも行われている。ふだん介護を行っている人(介護者)は2016年の段階で約699万人おり、1日あたりの平均介護時間は2時間29分であった(総務省『社会生活基本調査』)。中でも、65歳以上の介護者数は238万人と、5年前から57万人増加しており、いわゆる老老介護も増えている。
そこで、家庭内での介護(私的介護)について考えてみる。介護者人数と平均介護時間、介護に関連する職業の平均時給に基づいて、私的介護額を試算してみた。それによると、私的介護は1989年の4.6兆円から緩やかに増えており、2016年には6.8兆円に達している。その一方で、公的部門は同時期に0.5兆円から9.9兆円へと大幅に拡大した。高齢化が進む中で、私的介護の一部が公的介護に切り替わっていることが読み取れる。また、従来、私的介護などではカバーしきれなかった潜在的な需要が、公的介護によって満たされている可能性もある。つまり、介護サービスを利用している分だけ、社会保障の負担が増えるのは当然のことといえる。
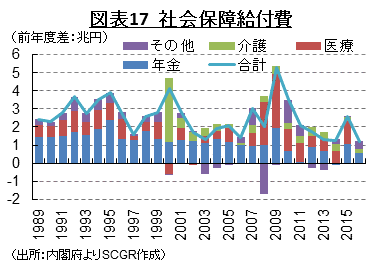
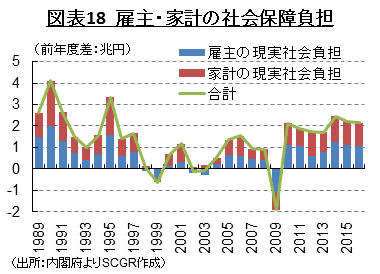
社会保障制度は、高齢者だけのものではない。図表17のように、社会保障制度は大別して、年金、医療、介護、その他に分けられる。その他には、子育て支援や雇用保険などが含まれている。例えば、失業率が上昇するなど不況期には雇用保険が生活を下支えしてきた。実際、リーマンショック後の不況期には、雇用保険からの給付が拡大したことは記憶に新しい。
また、今後、子育て支援がさらに拡充される見込みだ。社会保障制度も年金、医療、介護の3本柱から、子育てを含めた4本柱になっている。これも、昔の三世代世帯などでは手の空いた誰かが世話をしていた状況から、核家族化が進んだことに加え共働き世帯が増えたことによる保育所などの公的な機関の活用が進んだ結果で、私的扶養から社会的扶養への転換の一つの姿といえる。
ただし、社会保障制度には持続性の担保という課題もある。これまで、社会保障制度についても改革が行われてきた。2000年代には2004年の年金制度改革、2005年の介護制度改革、2006年の医療制度改革など一連の社会保障制度改革が実施された。社会保険料が毎年のように引き上げられ、雇主(企業)と家計の負担額が増えた。
また、2012年に社会保障と税の一体改革が行われ、消費税率も合わせて引き上げられるようになった。消費税収は、1999年度の予算総則から毎年度、年金・高齢者医療・介護などの高齢者3経費にあてることになった。さらに、2014年度からは法律が改正されて、子育てや現役世代医療を含めた社会保障4経費の財源として明記された。しかし、図表18のように、2000年代の負担増額は2兆円に届かなかった一方で、図表17の給付増額は2兆円前後だった。その差額は一般会計からの財源と積立金の運用収入などで対応することになる。つまり、十分な積立金をもたない医療制度や介護制度の維持のためには、効率化とともに、ある程度の保険料などの負担増からは逃れられないといえる。
こうした中で、社会保障給付などは、再分配効果を発揮してきたことが注目される。私的扶養の世界では、一般的な財やサービスと同じように、所得の多寡が消費の規模を決める。つまり、お金持ちほど多く消費できる世界である。
それに対して、社会保障制度は、いったん税や社会保険料として費用を支払うことで、必要な人が利用できるようにしている。例えば、病気になって医療サービスを必要とするから、そのサービスを受けられるのであって、所得の多寡ではない。その意味において、所得の再分配が働いている。
実際、図表19のように、世帯年齢の上昇や世帯人員数の減少などの影響もあって、世帯あたりの当初所得のジニ係数は上昇してきた。これは、所得格差が拡大してきたことを示している。非正規労働者数の増加なども一因ではあるものの、高齢化や世帯人数の減少などの影響も大きい。
その所得から社会保険料と税を支払って、年金などの社会保障給付、医療などの現物給付を受けた後の再分配所得は、大きく修正されている。1993年度から2014年度にかけて、ほぼ横ばい圏内にあり、再分配が機能していることがうかがえる。
このように、私的扶養から公助という社会的扶養に切り替えられる中で、再分配機能が働いてきた。その一方で、一般会計からの社会保障関連支出が拡大しており、財政赤字の一因になっているため、費用負担は遅れがちだった。そう考えると、費用負担の増加の必要性も認識できるだろう。
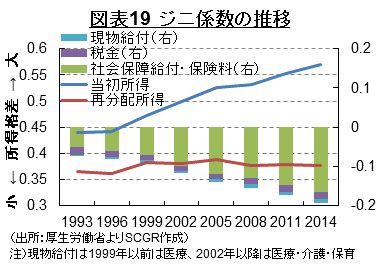
9. リスク①:移り変わったリスクの担い手
平成のはじめ、右肩上がりの世界があった時期には、リスクは成長の陰に隠れていた。例えば、1989年の完全失業率は2.3%で、職に大きな不安はなかった。景気も絶好調であり、右肩上がりの経済の中で、リスクとは無縁の世界で生きていると思うことができていた。
しかし、バブルが崩壊しただけではなく、1990年代には金融危機を通じて、大企業や金融機関でも普通に倒産することが明らかになった。また、リストラなどによって雇用機会を失うこと、就職氷河期が到来し、就職すらままならないことなどを経験した。その結果、これまで陰に隠れていて、認識しづらかったリスクが表にあらわれはじめた。そして、このリスクを、誰が引き受けるのかが問題になった。
これまでの日本では、政府はいわゆる「小さな政府」であり、リスクの引き受け手にはなれなかった。昭和の時代には、平均年齢も若く、リスクの引き受け手になる社会保障制度を現在ほど必要としていなかった。事実、1970年の平均年齢は、31.5歳であり(国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集』)、社会保障制度に大きく頼るような状況ではなかった。
また、経済がまだ成長期であったことから、社会保障よりもインフラ整備への需要が大きかった。そのため、限られた財源を社会保障よりも公共事業に回すことが社会全体からみて効率的とみなされていた。実際、図表20のように、政府の予算をみると、公共事業関係費と社会保障関係費(含む恩給関係費)の一般会計歳出総額に対する比率をみると、概ね35%前後で推移していることがわかる。1970年代から80年代にかけては、公共事業関係費の割合が大きかった。
しかし、平成になり、状況は大きく変わってきた。平均年齢は1990年に37.6歳、2000年に41.4歳、2010年には45歳となった。さらに、2020年には47.8歳へと上昇し、2030年には50歳に達すると推計されている。高齢化という面では、欧州をあっという間に追い抜いてしまい、この課題については世界のフロントランナーになっている。
高齢社会に直面したことで、社会保障関係費の割合が大きくなっている。つまり、政府は社会保障を通じて、リスクを軽減する方向に、舵を切らねばならなくなった。限られた財源で、社会保障に財源を回さねばならなかったので、より必要性が高い高齢者向け給付が重視され、現役世代への恩恵は二の次となった。その結果、現役世代向けの子育て支援、住宅支援などは手薄にならざるをえなかった。
ところが、そこは小さな政府の日本。十分な対応はとれていない。例えば、OECD加盟国(比較可能な30か国)の統計(OECD, National Accounts)をみると、2015年時点ですら、日本の政府総支出(対GDP比)は39.0%と上から24番目だった。それより下には、米国、ラトビア、オーストラリア、スイス、韓国、アイルランドしかいない。
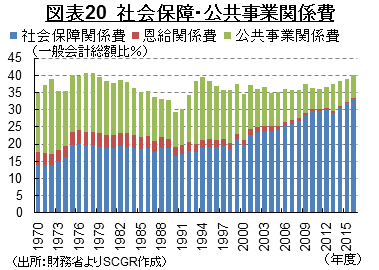
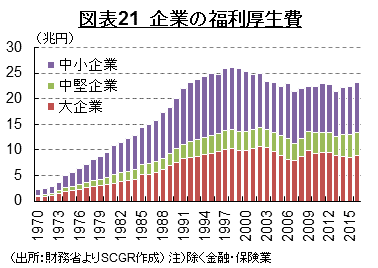
そのうち、社会保障支出(対GDP比)にかぎってみれば、日本(23.6%)は15番目と真ん中だが、最も高齢化が進んでいることを踏まえれば、1人あたりの社会保障給付は決して多いとはいえない。利払費を除く社会保障以外の支出では、日本(13.6%)は29番目で、それより下位にはアイルランドしかいない。社会保障以外は、米国よりも小さな政府であることがわかる(財務省『日本の財政関係資料』平成30年3月)。
また、今後も高齢化が進んでも、社会保障費が急拡大することは想定されていない。2018年度には経済成長によってGDPが増えた影響もあって、社会保障給付費(対GDP比)は21.5%、2025年度には現状投影ベース(ベースラインケース)で21.7~21.8%とほぼ変わらない。2040年度には23.8~24.1%とやや上昇する。2025年度の社会保障給付費は24.4%程度と見積もられており、高齢化の進展に社会保障給付が十分に追いつかない状況が想定されている(内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省『2040年を見据えた社会保障の将来見通し』(平成30年5月21日))。
国が面倒をみてこなかったというよりも、面倒をみる余裕はなかったという方が適切なのだろう。財政をみれば明らかなように、バブルまっただ中、あの絶頂期でようやく赤字国債を発行しなくて済むような構造だった。つまり、通常では、財政赤字の状態であり、大盤振る舞いできないのは当然のことといえる。
こうした状況下では、平成になるまで、リスクの担い手として、企業の役割は大きかった。例えば、雇用を守り、支払ってきた給料に加えて、家族手当や福利厚生費などが、リスク回避の上で政府の代替的な役割を果たしてきた。
図表21のように、平成の始めの頃まで、堅調に伸びてきた給料総額と歩調を合わせて増えてきた福利厚生費は、1990年代に入って増加ペースが鈍化し、1998年度に26.2兆円とピークを打った。その後、給料総額に合わせて変動しており、2013年度の21.5兆円まで減少トレンドにあった。1998年度と2013年度を比べると、従業員数が204.8万人増えたのに対して、福利厚生費は▲4.7兆円減少していた。厳しい状況の企業には、福利厚生費を増やすという選択肢はなかったとみられる。
企業が担えなくなったリスクは、家計が担わざるを得なくなった。さらに、失業率の上昇などが象徴するように、雇用の安定もなくなった。実際は、転職を経験する人が多かったにも関わらず、一部の大企業を中心に存在した「終身雇用」が日本全体にも存在するという幻想の中で安心感を持っていた人々は、平成を通じて、不況期にはリストラなどで職を失うこと、雇用リスクが現実のものであることを思い知るようになった。福利厚生などのコストは削減され、それらのリスクは労働者、すなわち家計に転嫁された。その結果、個人は高まるリスクに直面しながら、どのような道を選ぶのか問われることになっていった。
10. リスク②:消費にとって重石となった資産選択
リスクが高まる中で、より消費の足かせになるものには敏感になる。最も大きなものといえば、負債があげられる。借金が多ければ、その分新しい消費には躊躇するのが普通の人だからだ。
まず、図表22のように、平成になった当初、ほぼ同じ水準だった家計の負債残高と可処分所得総額は、バブル景気時の旺盛な消費を反映して、負債残高が上回るようになった。ただし、負債が増えたといっても、それと同時に所得が伸びていれば、消費を抑えつけるほどの大きな問題とは言い難い。
しかし、バブル崩壊とともに景気が減速、可処分所得が1980年代のようなペースで上昇しなくなった。高齢化が進んだことで、年金の存在感が拡大していることもある。景気が良いからといって、雇用者報酬ほど年金額が増えるわけではないこともあろう。賃金が上昇することによって、はじめて年金を受け取るときの金額である新規裁定年金額が引きあげられる一方で、それ以降は物価変動に応じて動くため、景気の良し悪しが年金所得に直接的に及ぼす影響は限られる。そうした所得の内訳の変化もあって、将来の所得増加が見込みにくくなった。
負債の負担感の拡大に拍車をかけたのは、デフレだ。1990年代後半から物価は伸び悩み、そのままデフレ状態に突入したため、むしろ負担感は見た目以上に大きくなった。例えば、世の中がインフレであっても、借金の元本は増えない。その一方で、インフレに伴って所得が増えれば、所得に対して借金は小さくなる。しかし、反対にデフレの中で、所得が伸び悩む、場合によって所得が減少すれば、借金の元本は変わらないので、負担感が大きくなる。
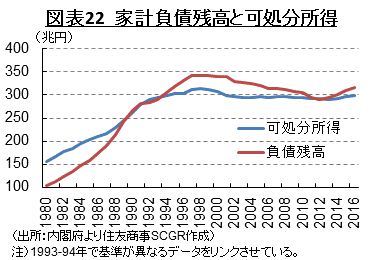
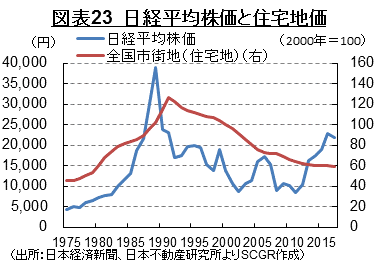
また、バブル崩壊が、資産価値を毀損した影響も大きい。もっとも顕著なのは株価だ。図表23のように、日経平均株価は、1989年をピークにして2000年代初めまで低下トレンドにあった。一時は4万円に迫るところまで上昇したものの、そこから下落、最悪期には1万円を大きく割り込んだ。いわゆるアベノミクス景気が始まってから株価は明確に上昇に転じたものの、平成が始まった当初のピークにはほど遠い状況に変わりない。つまり、キャピタルゲインなどが望みにくい状態にあり、家計は含み損を抱えつづけるしかなかった。こうした中では、株式購入による成功体験は、なかなか得られにくく、そのリスクが強く記憶に残っているのだろう。
また、かつてあった土地神話も崩壊してしまっている。全国市街地(住宅地)にみられるように、地価は下落基調にある。人口減少もはじまっており、地方ほど人が少ないから土地需要も少なく、地価が上がらない状況になってきた。また、工場などの生産拠点も海外に移転するなど、需要が弱い状況がつづいてきた。見方を変えると、売却しようにも、買い手がいないケースも少なくなかった。
リーマンショック前のプチ土地バブルも、あくまで「プチ」にすぎなかった。また、現在も、建設資材や人件費の高騰などからマンション価格も上昇しており、次第に手が出しにくい水準に到達しつつあることから、地価は上限に達しつつあるとの見方もある。そのため、足もとの地価の持ち直しも限定的な動きといえそうだ。
証券などの配当、預貯金の金利なども、見込みにくい状況になった。ゼロ金利政策、量的緩和政策など1990年代末からの金融緩和によって、金利はほぼゼロになっている。2016年にはマイナス金利政策が導入され、長期金利ですら、0%近傍になっているほどだ。そのため、預貯金は金利を期待するものではなく、安全に保管してくれる場所を提供してくれるものになっている。2018年7月末の金融政策決定会合では、2019年10月の消費税率引き上げの影響まで視野に入れることが明記されたため、当面金利は低い状態が続く。平成の3分の2はほぼ金利がない世界だったといえるだろう。
そこで、家計の金融資産と実物資産の実質収益率から資産選択について考えてみた。また、図表24のように、1980、1990、2000、2010年代までを含むように4つの年代区分を行った。
1980年代まではバブル景気の上り坂が含まれることもあって、株価上昇の影響などが大きい。金利も高かったので、証券や保険・年金などのリターンも期待できた。その一方で、住宅等や土地などの実質収益率の平均値もプラスだった。土地などの実物資産は、株式などに比べて売買しにくいこと、収益性とともに、実際に使うことが前提であることなどの相違もあって、実際の資産配分は、資産収益率の振れを最小にするような資産の組み合わせを表す「効率的フロンティア」から内側にある。ただし、それでも実質収益率は、プラスを維持していた。
それに対して、バブル崩壊を含む1990年代以降になると、株価が下落した影響が大きくなり、平均収益率が低下した一方で、変動幅が拡大、リスクが高まった。地価下落もあって土地価格の収益も低下して、マイナス圏に突入した。これ以降、土地は資産選択において足を引っ張る存在になっている。同じく住宅等についても、実質収益率が低下しており、実物資産が家計の資産選択において重石になっている様子が確認できる。例えば、住むために住宅を購入しているといっても、想定以上に住宅価格が下落すれば、それはリスクの種になりうる。実際の資産配分のリターンが1990年代にはほぼゼロになり、2000年代にはマイナスとなった。
そうしたリスクが高まる中において、実質的な収益率がマイナスである現金・預金の影響が強まっている。金利がつかない現金は、金利が低下するにしたがって、預金や他の証券との収益性の差が縮まってきた。また、株式や債券のように元本がなくなるリスクは通常想定されない。そのため、経済などに先行き不透明感が高まる中では、安全性という面で現金が選好された可能性がある。
さらに、デフレによって、物価上昇による実質収益率の下押しが軽減していることも、現金保有の追い風になってきた。先にみたように、生活リスクが高まってきた中では、リスク回避の傾向が強まる。そうした環境における資産選択において、リスクが低い現金・預金が選好されるようになったと考えられる。
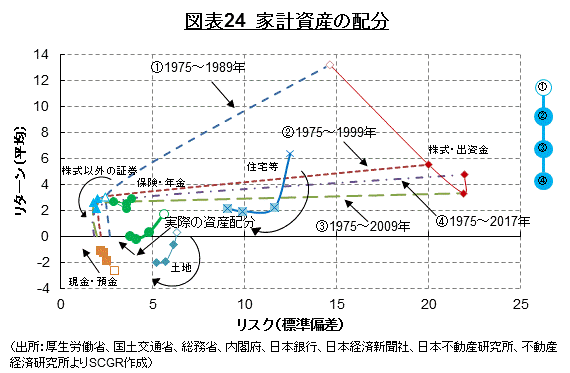
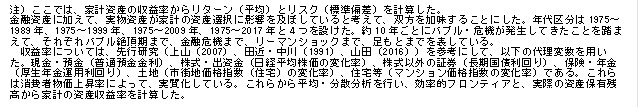
ただし、2010年代になると、こうした動きに変化がみられるようになった。まず、日経平均株価の持ち直しにみられるように、株式・出資金のリターンの回復だ。株式以外の証券や保険・年金は、低金利政策によってリターンは縮小したものの、2000年代から大きく崩れていない。むしろ変動幅が縮小しており、相対的な安全性が高まっているようにみえる。また、住宅等の収益性の下げ止まりや、土地の下落幅の縮小など、実物資産による重石も緩やかに軽減しつつある。その結果、実際の資産配分のリターンはマイナス圏からほぼゼロに回復しつつある。このトレンドが続いて、リスクが軽減していくのか、それとも再びリスクが高まるのかが、今後の消費に大きな影響を及ぼすだろう。
このようなリスクを目の当たりにしたとき、人々の消費行動は慎重にならざるを得ないのではないだろうか。言い換えれば、賢い消費という選択をするようになった可能性があるだろう。
そこで、将来期待される所得、保有する資産(土地や住宅等)、現在の所得によって、消費額が決まるという関係を想定して、消費関数を推計してみた。図表25のように、実物資産が2000年代の消費の足を引っ張っていた様子が確認できる。不況期での資産価格の低下が、消費に下押し圧力をかけるのは自然な流れといえる。ところが、2000年代前半の戦後最長の景気を記録していた時期に、実物資産が消費に下押し圧力をかけていた可能性が示唆される。つまり、家計にとって、平成がはじまった当初金融資産、実物資産とみなされていたものが、家計の足を引っ張る存在、すくなくとも資産効果を生み出すものではなくなってしまっていたということだ。
ただし、足もとにかけて徐々に環境は変化しつつある。前述のように、家計資産の実質収益率はマイナス圏から脱しつつあり、次第に家計の負担は軽減されてきている。その結果、消費への下押し圧力も緩まっており、株価の上昇期にはむしろ消費を押し上げる要因にもなっている。こうした変化の兆しも、消費にとっては重要な要因だろう。
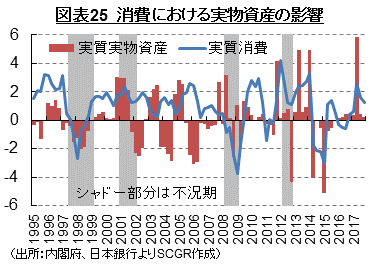
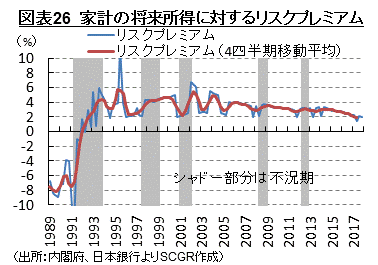
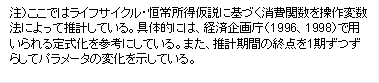
11. リスクから学び取った堅実さ
平成の閉塞の中で、将来の所得に対するリスクを消費者は感じ取るようになっていた。将来の自分の所得に対する不確実性が高まることによって、将来得られるであろう所得を過度に割り引いて考えるようになる。そのリスクへの感度を、ここではリスクプレミアムとして捉える。前述の消費関数に基づき、消費者が感じ取っているリスクへの感度(リスクプレミアム)を推計してみた。
その結果、図表26のように、バブル崩壊時の不況期に一気にリスクプレミアムが上昇しており、消費を抑えて貯蓄に回すインセンティブが働きやすくなったといえる。その後の景気回復とともに、リスクプレミアムは低下するものの、1990年代後半の金融危機やアジア通貨危機のさなか、大手金融機関が経営破たん、完全失業率も上昇し、企業もリストラという名の人員削減を進めたことで、再びリスクプレミアムが高まった。
2000年代には、戦後最長となる景気拡大の中で緩やかにリスクプレミアムは低下したものの、2008年にはリーマンショック後の世界同時不況に遭遇、約10年周期で大きな不況に見舞われ、消費者は警戒感を緩めることができなかった。米国でも、定期的にバブルとその崩壊が発生していた。
しかし、日本では1990年のバブル以降、バブルというほど盛り上がらないうちに、崩壊に直面している。2008年の世界同時不況では、直接的な影響というよりも、むしろグローバルサプライチェーンに組み込まれていたことで、間接的に悪影響が押し寄せてきたといえる。
また、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災などの自然災害も、将来への不安を引き起こす一因になっていたと考えられる。それ以外にも、平成をふりかえると、自然災害が多く発生しており、人々の意思決定に影を落としてきた。
将来の所得増加を期待しないため、消費額を大きく増やすという選択肢はない。必要なものを吟味し、購入する。浮かれすぎたバブル期への反省もあって、そうした慎重な姿勢が広がってきたようだ。特に、不況期に就職すると、初めて自分で自由に使えるお金を手にしたときの消費行動が習慣として根づく傾向があるともいわれており、1990年代後半から2000年代前半にかけて、就職氷河期を経験した若年世代への影響が大きいとみられる。
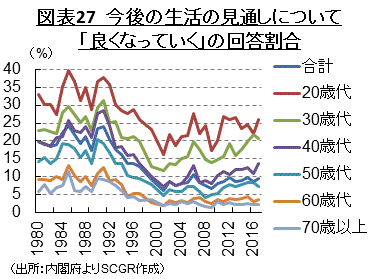
そうしたマインド変化に加えて、雇用環境自体も変化してきた。不況というだけではなく、就職氷河期を伴うと、その影響は深刻だった。就職が難しいことに加えて、いったん非正規労働者として就職すると、その後に正規雇用への転換が難しいことが一般的に知られるようになった。そうなると、単なるリスク回避ではなくなり、実際に消費が伸び悩むことを経験することによって、さらにリスクへの感度を高めてしまうことになりかねない。
かつての右肩上がりの世界では、自分の親の所得を超えていくことができた。しかし、伸び悩むくらいならばまだマシという所得環境の中では、自分の親の所得を超える難易度が高まった。それによって、良く言えば堅実で慎重、悪く言えば、自由がきかないという消費行動を取らざるを得なくなってしまった。
こうしたリスクプレミアムの上昇にあらわれる消費を抑制するマインドに、実際に増えにくい所得、資産価格の低下などが重なったことが、消費の伸び悩みに拍車をかけた。
しかし、状況は好転しつつあるようだ。10年ごとに起きていた大きなショックが2017年には回避できた。2012年末からの景気拡張局面に、アベノミクス効果が重なり、これまで覆い隠されてきた人手不足があらわになった。政労使三者協議によって、デフレ均衡というべき状況から、日本経済は抜け出すことができたようだ。ベースアップが真剣に議論されるようになり、企業も労働者も、賃金は上昇するものであったことを思い出した。そうした変化が、一時的なものではなく、複数年続くという経験が徐々に蓄積しつつあって、家計のリスクプレミアムは低下している。つまり、消費に対してより積極的になってもよいのではないかというサインといえる。
実際、図表27のように、今後の生活の見通しについて「良くなっていく」という回答が足もとで増えてきている。特に、20歳代、30歳代の若い世代の将来見通しが改善していることが注目される。これからの世界を担う若い世代、特に、アベノミクス景気回復期に就職した20歳代とともに、バブルを知る世代もまた消費の牽引役になれるのか、消費が再点火するきっかけはそのあたりにありそうだ。
12. 平成から次の時代の消費へ
このように、バブル絶頂から始まった平成も、多くの試練を経る中で、消費の伸び悩む姿がありふれた光景になっていた。しかし、その平成も終わりに近づくにつれて、総決算といわんばかりに、状況は好転しつつある。
景気回復の中で、賃金は上昇しており、将来に期待を持っても悪くない状況になっている。資産価格の持ち直しも、これまで背負ってきた重荷をいくらか軽くしている。高齢化などがあるものの、社会保障制度が力を発揮しており、個人のリスクを軽減している。もちろん、社会保険料や消費税などの負担増はあるものの、再分配効果が効いており、不平等さの広がりに一定の歯止めをかけている。消費者マインドも改善し、未来志向も回復しつつあり、将来に対するリスクを過度に見積もる傾向も弱まっている。
平成が始まった当初のバブル期の再来は不可能であるものの、個人消費を巡る環境は、それなりに良好なものになってきて、ようやく消費に前向きになれる状態になりつつある。平成は、昭和の右肩上がりの世界からの軌道修正の時期であり、平成の終わりに近づいて、消費はようやく新たな成長へと向かいつつあるようだ。
<参考文献>
上山仁恵(2007)「実物資産を含めた家計の資産選択の効率性」、『日本福祉大学経済論集』第34号pp.129-143.
経済企画庁(1996)『経済白書(平成8年版)』.
経済企画庁(1998)『経済白書(平成10年版)』.
厚生労働省(2012)『厚生労働白書(平成24年版)』.
税制調査会(2004)「参考資料~我が国経済・社会の構造変化の『実像』把握(3)≪価値観・ライフスタイル」」(第8回基礎問題小委員会(3月16日)資料.
田近栄治・中川和明(1991)「わが国家計の資産選択と資産需要の代替性」『フィナンシャル・レビュー』第20号pp.67-83.
山田直夫(2016)「家計の資産選択と金融所得課税」『フィナンシャル・レビュー』第127号pp.77-95.
以上
記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。
 レポート・コラム
レポート・コラム
 SCGRランキング
SCGRランキング
- 2025年4月22日(火)
ラジオNIKKEI第1『マーケット・トレンドDX』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が出演しました。 - 2025年4月21日(月)
『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年4月19日(土)
『毎日新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年4月18日(金)
『週刊金融財政事情』2025年4月22日号に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年4月16日(水)
日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。

